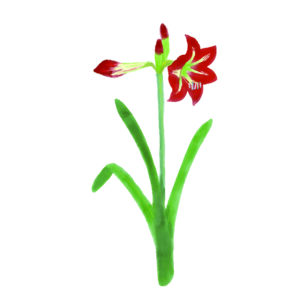はじめに
建設業法第26条の2から第26条の4は、建設工事における技術者配置制度の重要な補完規定である。第26条が主任技術者・監理技術者の配置義務を定めているのに対し、これらの条文は、一式工事業者が専門工事を施工する場合の許可要件、特定専門工事における技術者兼任の特例、そして技術者の具体的職務内容を規定している。
本稿では、国土交通省の建設業法令遵守ガイドラインおよび関連通知を参照しながら、これら3つの条文を実務的観点から詳細に解説する。
第1章 第26条の2(一式工事業者の専門工事施工制限)の解説
1-1. 条文の趣旨と制度の背景
第26条の2は、土木一式工事または建築一式工事を営む業者が、専門工事を施工する際の要件を定めた規定である。
一式工事とは、総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物または建築物を建設する工事を指す。これに対し、専門工事は電気工事、管工事、鋼構造物工事など、特定の専門技術を要する工事である。
本条の立法趣旨は、一式工事業の許可を持つだけでは専門工事の技術的能力が担保されないため、専門工事を施工する場合には、適切な技術者の配置または専門業者への発注を義務付けることにある。
1-2. 第1項の規定内容
【条文の構造】
第1項は、土木工事業または建築工事業を営む者が土木一式工事または建築一式工事を施工する際、その中で専門工事を施工する場合の要件を定めている。
【施工可能な2つの方法】
専門工事を施工できるのは、以下のいずれかの場合に限られる。
(1) 有資格技術者を配置して自ら施工する場合
第7条第2号イ、ロまたはハに該当する者(一定の資格または実務経験を有する技術者)で、当該専門工事の技術上の管理をつかさどる者を配置する場合である。
具体的には以下の者を指す。
- イ:国家資格者等(1級・2級技術検定合格者、技術士等)
- ロ:所定学科修了者で一定の実務経験を有する者
- ハ:10年以上の実務経験を有する者
これらの者を工事現場に配置することで、専門工事の適正な施工管理が可能となる。
(2) 専門業者に発注する場合
当該専門工事に係る建設業の許可を受けた建設業者に施工させる場合である。この場合、一式工事業者は元請として総合的な管理を行い、実際の専門工事施工は専門業者が担当する。
【軽微な建設工事の除外】
第3条第1項ただし書の政令で定める軽微な建設工事は、本条の規制対象から除外される。軽微な建設工事とは、建設業法施行令第1条の2に定める以下のものである。
- 建築一式工事:工事1件の請負代金が1,500万円未満または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事
- その他の工事:工事1件の請負代金が500万円未満の工事
1-3. 第2項の規定内容(附帯工事)
【附帯工事の定義】
第2項は、建設業者が許可を受けた建設業に係る建設工事に「附帯する」他の建設工事を施工する場合の要件を定めている。
附帯工事とは、主たる建設工事の施工に伴い、その工事を完成させるために必要となる従たる工事を指す。国土交通省の解釈では、主たる工事と密接な関連性があり、主たる工事の施工に付随して一体的に施工することが合理的な工事とされている。
【附帯工事の具体例】
電気工事業者が電気工事に附帯して行う軽微な内装仕上工事、管工事業者が配管工事に附帯して行う床・壁の開口・補修工事などが該当する。
【第1項との共通点】
第2項も第1項と同様、有資格技術者を配置して自ら施工するか、専門業者に発注するかのいずれかの方法によることを求めている。
1-4. 実務上の留意点
【許可業種の確認義務】
一式工事業者が専門工事を施工する際には、まず自社の建設業許可業種を確認する必要がある。専門工事の許可を取得していない場合、本条の要件を満たさなければならない。
【技術者の専任要件との関係】
第26条第3項により、請負代金が一定額以上の工事では技術者の専任配置が求められる。本条の技術者配置と専任要件の双方を満たす必要がある点に注意が必要である。
【下請契約における適用】
本条は元請・下請を問わず適用される。下請業者が一式工事を請け負い、その中で専門工事を施工する場合にも、本条の要件が適用される。
【国土交通省のガイドライン】
国土交通省「建設業法令遵守ガイドライン」では、一式工事業者が安易に専門工事を自社施工することによる品質低下や安全管理不全を防止するため、本条の厳格な運用を求めている。
第2章 第26条の3(特定専門工事における技術者兼任制度)の解説
2-1. 条文の趣旨と制度創設の経緯
第26条の3は、平成26年(2014年)の建設業法改正により新設された規定である。
【制度創設の背景】
建設業における技術者不足が深刻化する中、施工技術が画一的で効率化が可能な専門工事について、元請の主任技術者が下請の主任技術者の職務も兼ねることを認めることで、技術者配置の合理化と施工効率の向上を図ることが目的とされた。
【制度の基本構造】
本制度は、一定の要件を満たす「特定専門工事」において、元請と下請が合意し、発注者の承諾を得ることで、元請の主任技術者が下請の主任技術者の職務も併せて行うことを認めるものである。
2-2. 第1項の規定内容(兼任制度の基本)
【適用される当事者】
本制度が適用されるのは、特定専門工事の元請負人と下請負人である。ただし、下請負人は建設業者である場合に限られる。建設業許可を持たない者が下請となる場合には本制度は適用されない。
【兼任の効果】
元請と下請の合意により、元請が配置する主任技術者が、下請が配置すべき主任技術者の職務も併せて行うことができる。この場合、下請は第26条第1項の規定にかかわらず、主任技術者を配置する必要がなくなる。
【職務の内容】
兼任される職務は、次条第1項に規定する主任技術者の職務、すなわち、施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理および施工従事者の技術上の指導監督である。
2-3. 第2項の規定内容(特定専門工事の定義)
【特定専門工事の要件】
特定専門工事とは、以下のすべての要件を満たす工事である。
(1) 土木一式工事または建築一式工事以外の建設工事であること
一式工事は対象外であり、専門工事のみが対象となる。
(2) 施工技術が画一的であること
工事の施工方法や技術が標準化されており、特殊な技術判断を要しない工事である。
(3) 施工の技術上の管理の効率化を図る必要があるものとして政令で定めるもの
建設業法施行令第27条の4により、以下の3業種が指定されている。
- 鉄筋工事
- 型枠工事
- 内装仕上工事
(4) 下請契約の請負代金の額が政令で定める金額未満
建設業法施行令第27条の4第2項により、下請契約の総額が3,500万円未満(建築一式工事の場合は7,000万円未満に相当)の工事とされている。
(5) 元請工事が一定規模以上でないこと(除外要件)
元請負人が発注者から直接請け負った建設工事で、下請契約の請負代金の額が第26条第2項に規定する金額以上(4,000万円以上、建築一式工事は6,000万円以上)となるものは除外される。
2-4. 第3項・第4項の規定内容(合意の方式)
【書面による合意の原則】
第3項は、元請と下請の合意を書面により行うことを義務付けている。
記載すべき事項は国土交通省令で定められており、建設業法施行規則第17条の2により以下が規定されている。
- 特定専門工事の内容
- 元請負人が置く主任技術者の氏名
- 合意の有効期間
- その他必要な事項
【電子的方法による合意】
第4項は、書面に代えて電子情報処理組織を使用する方法等により合意できることを定めている。電子契約やメール等による合意も可能であり、この場合は書面による合意とみなされる。
2-5. 第5項・第6項の規定内容(発注者の承諾)
【発注者承諾の必要性】
第5項は、元請負人が本制度を利用しようとする場合、あらかじめ発注者の書面による承諾を得ることを義務付けている。
この承諾は、下請の技術者配置が不要となることから、発注者が工事の品質・安全管理体制を確認・了解する趣旨である。
【発注者承諾の方式】
第6項により、発注者も電子的方法により承諾の通知をすることが可能である。
【国土交通省の運用指針】
国土交通省の通知では、公共工事において本制度を活用する場合、発注者は工事の規模・難易度、元請の技術力等を総合的に勘案して承諾の可否を判断するよう求めている。
2-6. 第7項の規定内容(兼任技術者の要件)
【特別な資格要件】
兼任する元請の主任技術者には、通常の主任技術者以上の要件が課されている。
(1) 指導監督的実務経験(第1号)
当該特定専門工事と同一種類の建設工事に関し、1年以上の指導監督的な実務経験を有することが求められる。
「指導監督的な実務経験」とは、単なる施工経験ではなく、技術者として他の作業員を指導・監督した経験を指す。国土交通省の解釈では、主任技術者や現場代理人としての経験がこれに該当するとされている。
(2) 専任配置(第2号)
当該特定専門工事の工事現場に専任で配置されることが必要である。
第26条第3項の専任要件とは別に、本制度を利用する場合には、工事規模にかかわらず専任配置が義務付けられている。
2-7. 第8項・第9項の規定内容(適用除外と再下請禁止)
【第26条第3項の適用除外】
第8項により、兼任技術者については第26条第3項の規定(専任要件)が適用されない。これは、第7項第2号で既に専任配置が義務付けられているためである。
【再下請の禁止】
第9項は、本制度を利用する下請負人が、その下請負に係る建設工事を他人に請け負わせること(再下請)を禁止している。
この禁止規定は、技術者配置の合理化による効果が、再下請により不明確になることを防止する趣旨である。国土交通省の通知では、この禁止に違反した場合、監督処分の対象となることが明示されている。
2-8. 実務上の留意点と活用事例
【制度活用のメリット】
本制度を活用することで、下請業者は主任技術者の配置が不要となり、人材不足への対応や工事原価の低減が可能となる。また、元請が一元的に技術管理を行うことで、品質の均質化や工程管理の効率化も期待できる。
【活用が想定される場面】
大規模な建築工事において、鉄筋工事、型枠工事、内装仕上工事の各専門工事を施工する場合、元請のゼネコンが配置する主任技術者がこれらの工事を一元的に管理する形態が典型例である。
【注意すべき実務上のポイント】
合意書の作成と保管、発注者承諾の取得時期、兼任技術者の資格確認、再下請禁止の徹底などが重要である。特に、公共工事では発注者承諾の手続きを工事着手前に完了しておく必要がある。
第3章 第26条の4(主任技術者及び監理技術者の職務等)の解説
3-1. 条文の趣旨と規定の意義
第26条の4は、平成26年の建設業法改正により新設された規定であり、主任技術者および監理技術者の職務内容を明文化したものである。
【明文化の必要性】
従来、技術者の職務内容は建設業法上明確に規定されておらず、通達や運用指針で示されていた。しかし、技術者の役割の重要性に鑑み、その職務を法律上明確にする必要性が認識され、本条が制定された。
【建設工事の品質確保との関係】
本条は、建設工事の適正な施工を確保するため、技術者が果たすべき職務を具体的に定めることで、工事の品質・安全管理体制を明確化している。
3-2. 第1項の規定内容(技術者の職務)
【職務の目的】
主任技術者および監理技術者は、「工事現場における建設工事を適正に実施するため」に職務を行う。これは、単に形式的に技術者を配置するだけでなく、実質的に適正な施工管理を行うことを求める趣旨である。
【具体的職務内容】
本項は、技術者の職務として以下の事項を列挙している。
(1) 施工計画の作成
工事の施工方法、工程、資材・機械の調達計画、安全管理計画等を記載した施工計画書を作成する職務である。国土交通省の「公共建築工事標準仕様書」では、施工計画書の記載事項として、工事概要、現場組織、安全管理、品質管理、環境対策等が示されている。
(2) 工程管理
工事の進捗状況を把握し、予定工程と実際の進捗を比較・分析し、必要に応じて工程の調整を行う職務である。
(3) 品質管理
使用材料の品質確認、施工の各段階における品質検査、不良箇所の是正指示等を行い、工事の品質を確保する職務である。
(4) その他の技術上の管理
上記以外の技術上の管理として、出来形管理、安全管理、環境管理等が含まれる。国土交通省の通知では、安全衛生管理についても技術者の重要な職務とされている。
(5) 施工従事者の技術上の指導監督
工事現場で施工に従事する作業員等に対し、適切な施工方法の指示、作業の監視、不適切な施工の是正等を行う職務である。
【誠実義務】
本項は、これらの職務を「誠実に行わなければならない」と規定している。これは、形式的・表面的な職務遂行ではなく、実質的に工事の品質・安全を確保する姿勢を求めるものである。
3-3. 第2項の規定内容(施工従事者の義務)
【指導に従う義務】
第2項は、工事現場における建設工事の施工に従事する者に対し、主任技術者または監理技術者がその職務として行う指導に従う義務を課している。
【義務の主体】
「施工に従事する者」には、元請・下請を問わず、当該工事現場で実際に施工に携わるすべての作業員が含まれる。
【職務としての指導】
従う義務が課されるのは、技術者が「その職務として行う指導」である。技術者の個人的な指示や、職務の範囲を逸脱した指示には従う義務は生じない。
【違反の効果】
本項違反は、直ちに罰則の対象とはならないが、工事の適正な施工を妨げる行為として、元請業者や下請業者に対する監督処分の理由となり得る。国土交通省の通知では、技術者の指導に従わない作業員がいる場合、技術者は当該作業員の交代を求めることができるとされている。
3-4. 国土交通省のガイドラインと運用実態
【建設業法令遵守ガイドライン】
国土交通省「建設業法令遵守ガイドライン」では、主任技術者・監理技術者の職務について詳細な解説がなされている。
同ガイドラインは、技術者が実質的に職務を遂行できる体制の整備、技術者の権限の明確化、施工体制台帳への記載の徹底等を求めている。
【監理技術者講習】
監理技術者資格者証の交付を受けた者は、5年ごとに国土交通大臣の登録を受けた講習機関が行う講習を受講しなければならない。この講習では、本条の職務内容に関する最新の知見や事例が提供されている。
【公共工事における運用】
公共工事では、工事成績評定において技術者の職務遂行状況が評価項目とされている。施工計画書の内容、工程管理の適切性、品質管理の実施状況等が具体的に審査される。
3-5. 実務上の留意点
【職務遂行の記録化】
技術者の職務遂行状況を記録・保管することが重要である。施工計画書、品質管理記録、安全パトロール記録、作業日報等により、技術者が実質的に職務を遂行していることを証明できるようにすべきである。
【専任技術者の配置との関係】
第26条第3項により専任配置が求められる技術者は、本条の職務を現場に常駐して行うことが求められる。他の工事現場との兼任や、本社業務との兼任は認められない。
【下請技術者との連携】
元請の技術者は、下請の技術者とも密接に連携し、工事全体の技術管理を統括する必要がある。定期的な技術者会議の開催、情報共有体制の構築等が求められる。
【技術者の権限の明確化】
技術者が職務を適切に遂行するためには、工事に関する一定の権限が付与されている必要がある。工事契約書や社内規程において、技術者の権限を明確にすることが望ましい。
第4章 関連判例・行政処分事例
4-1. 技術者配置義務違反に関する判例
【最高裁判例の示した基準】
建設業法における技術者配置義務に関しては、いくつかの重要な判例が存在する。最高裁は、技術者配置義務が「形式的な配置ではなく、実質的に職務を遂行できる体制の確保」を求めるものであることを明確にしている。
【専任違反が争われた事例】
ある裁判例では、主任技術者として届け出た者が実際には他の工事現場に常駐しており、当該工事現場にはほとんど立ち会っていなかったケースで、建設業法違反による営業停止処分が適法とされた。
裁判所は、専任配置とは「工事現場に常駐し、専ら当該工事の技術上の管理を行うこと」を意味し、名目的な配置は許されないと判示している。
4-2. 一式工事業者の専門工事施工に関する行政処分事例
【国土交通省による監督処分事例】
第26条の2違反については、国土交通省および都道府県による監督処分事例が多数存在する。
典型的な違反事例としては、建築一式工事の許可のみを持つ業者が、電気工事の許可を持たずに、かつ有資格技術者の配置もないまま電気工事を自社施工したケースがある。このような事例では、営業停止処分が科されている。
【違反の発覚経緯】
これらの違反は、労働災害の発生時、公共工事の施工体制点検時、または通報により発覚することが多い。
4-3. 特定専門工事における技術者兼任制度の運用事例
【制度の活用実態】
第26条の3の特定専門工事における技術者兼任制度は、制度創設後、大手ゼネコンを中心に徐々に活用が広がっている。
国土交通省の調査によれば、特に鉄筋工事と型枠工事において本制度の活用が進んでおり、技術者不足への対応と工事原価低減の効果が確認されている。
【公共工事での活用事例】
公共工事においても、発注者が本制度の趣旨を理解し、適切な審査を経て承諾するケースが増加している。ただし、工事の規模や複雑性によっては、発注者が承諾を留保する場合もある。
4-4. 技術者の職務不履行に関する行政処分事例
【職務不履行が問題となった事例】
主任技術者または監理技術者が配置されていても、実質的に職務を履行していなかったことが問題となった事例がある。
ある事例では、監理技術者として届け出た者が施工計画書を作成せず、品質管理や安全管理も不十分であったため、重大な施工不良が発生した。この事例では、元請業者に対し営業停止処分が科されるとともに、当該監理技術者の資格者証が取り上げられた。
【施工体制台帳の不備】
技術者の配置状況を記載する施工体制台帳の記載が不正確または不十分であった場合も、監督処分の対象となる。特に、専任配置が必要な技術者について、他工事との兼任実態があるにもかかわらず専任と記載していた事例では、重い処分が科されている。
第5章 コンプライアンス上の実務的留意点
5-1. 技術者配置に関するコンプライアンス体制の構築
【社内管理体制の整備】
建設業者は、技術者配置に関する法令遵守を徹底するため、以下のような社内管理体制を整備すべきである。
(1) 技術者台帳の整備
自社が雇用する技術者の資格、実務経験、現在の配置状況を一元管理する台帳を整備する。これにより、適切な技術者配置計画が可能となる。
(2) 配置決定の承認プロセス
技術者の配置を決定する際、工事内容と技術者の資格・経験を照合し、法令要件を満たしているかを確認する承認プロセスを確立する。
(3) 定期的な配置状況の確認
工事進行中も、技術者が実際に職務を遂行しているかを定期的に確認する仕組みを設ける。現場巡回、報告書の確認、施工記録の査閲等により、形骸化を防止する。
【コンプライアンス教育の実施】
技術者本人はもちろん、経営層、営業担当者、工事担当者に対し、建設業法の技術者配置義務に関する教育を定期的に実施することが重要である。
特に、専任配置の意義、一式工事業者の専門工事施工制限、技術者の職務内容等について、具体的な事例を交えた研修が効果的である。
5-2. 一式工事業者における専門工事施工管理
【許可業種の確認と追加取得の検討】
建築一式工事または土木一式工事の許可のみを持つ業者が専門工事を施工する機会が多い場合、専門工事の許可を追加取得することを検討すべきである。
許可取得により、第26条の2の制約を受けずに専門工事を施工できるようになり、技術者配置の柔軟性が高まる。
【有資格技術者の確保・育成】
専門工事の許可取得が困難な場合でも、各種の専門工事に対応できる有資格技術者を確保・育成することで、自社施工の範囲を拡大できる。
技術検定の受検支援、実務経験の計画的な積み上げ等、人材育成計画を策定することが望ましい。
【適切な下請発注】
自社での施工が困難な専門工事については、適切な許可を持つ専門業者に発注する。この際、下請業者の許可業種、技術者配置状況、施工能力等を十分に確認することが重要である。
5-3. 特定専門工事における技術者兼任制度の活用
【制度活用の判断基準】
本制度を活用するかどうかは、以下の要素を総合的に勘案して判断すべきである。
- 工事の規模と複雑性
- 元請技術者の能力と経験
- 下請業者との信頼関係
- 発注者の意向
- コスト削減効果
【適切な手続きの履行】
本制度を活用する場合、書面による合意の作成、発注者承諾の取得、兼任技術者の資格確認等、法定の手続きを確実に履行する必要がある。
特に、公共工事では手続きの時期や方法について発注者の指示に従うことが重要である。
【再下請禁止の徹底】
本制度を利用する下請業者は再下請が禁止されている。この点を契約書に明記し、違反がないよう管理する必要がある。
5-4. 技術者の職務遂行の実効性確保
【職務遂行環境の整備】
技術者が職務を適切に遂行できるよう、以下のような環境を整備すべきである。
- 十分な権限の付与
- 必要な情報の提供
- 補助要員の配置
- 適切な労働時間管理
【職務遂行状況のモニタリング】
技術者の職務遂行状況を適切にモニタリングする仕組みを構築する。施工計画書の内容審査、定期的な現場巡回、品質管理記録の確認等により、職務が適切に履行されているかを確認する。
【問題発生時の対応】
技術者の職務遂行に問題が発見された場合、速やかに是正措置を講じる。必要に応じて技術者の交代、追加配置、外部専門家の活用等を検討する。
5-5. 内部監査とコンプライアンスチェック
【定期的な内部監査の実施】
建設業者は、技術者配置に関する法令遵守状況について、定期的に内部監査を実施すべきである。
監査項目としては、技術者の資格確認、配置状況の確認、職務遂行記録の確認、施工体制台帳の記載内容確認等が挙げられる。
【コンプライアンスチェックリストの活用】
工事着手時、工事進行中、工事完了時等の各段階で、技術者配置に関するコンプライアンスチェックリストを用いて確認を行うことが効果的である。
【外部専門家の活用】
必要に応じて、建設業法に精通した弁護士、行政書士、コンプライアンス専門家等の外部専門家によるチェックや助言を受けることも有効である。
おわりに
建設業法第26条の2から第26条の4は、建設工事における技術者配置制度の重要な補完規定である。
第26条の2は、一式工事業者が専門工事を施工する際の制限を定め、適切な技術者配置または専門業者への発注を義務付けることで、工事の品質と安全を確保している。
第26条の3は、特定専門工事における技術者兼任制度を定め、技術者不足への対応と施工効率の向上を可能としている。
第26条の4は、主任技術者および監理技術者の具体的職務を明文化し、技術者の役割と責任を明確にしている。
これらの規定を正確に理解し、適切に運用することは、建設業者にとって極めて重要である。法令遵守は、行政処分を回避するためだけでなく、工事の品質・安全を確保し、発注者・社会からの信頼を獲得するための基盤である。
本稿で解説した内容を参考に、各建設業者においては、技術者配置に関する適切なコンプライアンス体制を構築されることを期待する。
建設業コンプライアンス研修のご案内
建設業法の技術者配置義務や専門工事施工制限など、建設業特有の法令遵守は複雑かつ重要性が高く、実務での正確な理解と運用が求められます。
中川総合法務オフィス(https://compliance21.com/)代表の中川恒信は、建設業を含む様々な業種で850回を超えるコンプライアンス研修を担当してきた実績を持つ、コンプライアンスとリスクマネジメントの専門家です。
私たちの強み
- 豊富な実務経験:不祥事を起こした組織のコンプライアンス態勢再構築を実際に支援し、組織改革の現場を熟知
- 内部通報の外部窓口:現在進行形で複数企業の内部通報外部窓口を担当し、現場の生の声を把握
- マスコミからの信頼:不祥事企業の再発防止策について、マスコミからしばしば意見を求められる第一線の専門家
- 建設業界への深い理解:建設業法をはじめとする業界特有の法規制と実務慣行を踏まえた実践的な指導
ご提供する研修・コンサルティング
本記事で解説した技術者配置義務、一式工事業者の専門工事施工制限、特定専門工事における技術者兼任制度など、建設業法の重要ポイントについて、貴社の実情に合わせた研修プログラムをご提供いたします。
また、コンプライアンス体制の構築、内部通報制度の整備、不祥事発生時の危機管理など、幅広いテーマでのコンサルティングも承っております。
研修費用
1回30万円(+消費税)を原則としております。 ※研修内容、時間、参加人数等により、別途お見積りいたします。
お問い合わせ
建設業関係企業等のコンプライアンス研修、リスクマネジメント研修、コンサルティングに関するお問い合わせは、以下の方法で承っております。
電話:075-955-0307 相談フォーム:https://compliance21.com/contact/
貴社の持続的発展と社会的信頼の向上のため、ぜひ一度ご相談ください。
中川総合法務オフィス https://compliance21.com/ 代表 中川恒信