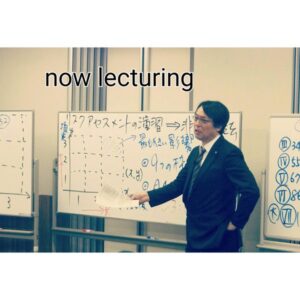相続ワンストップサービスプロ養成講座|2025年問題に対応した相続専門家を育成
相続ワンストップサービスプロ養成講座は、2025年問題と相続登記義務化に対応する京都・大阪の相続専門家を育成する実践的な講座です。1000件超の相続相談実績を有する中川総合法務オフィスが、オンライン個別指導により地域ナンバーワンの相続アドバイザーを養成いたします。
「現場が分かる建設業法全条文解説 第1条(目的)」~工事現場から契約書まで、実務で使える逐条解説~
建設業法第1条は、発注者保護と建設工事の適正施工を通じて建設業の健全な発達を図り、ひいては公共の福祉の増進に資することを目的とするものであり、この目的条文の趣旨を踏まえて建設業許可制度や各種規制のコンプライアンスを徹底することが、実務上の「建設業法解説」においても極めて重要である。
「現場が分かる建設業法全条文解説 第2条(定義)」~工事現場から契約書まで、実務で使える逐条解説~
建設業法第2条は「建設工事」「建設業」「建設業者」「下請契約」「発注者」など、建設業に関する基本概念を定義している。本条を正確に理解することは、建設業のコンプライアンスとリスクマネジメントの第一歩である。
法定相続人が誰もいない事例が令和時代に急増しているが次のケースでは債権回収や土地購入はどうすれば可能なのか。
【故人の戸籍謄本などを時代を遡って精査しても第三順位もいない可能性ある事が増えてきている】⇒相続財産は法人となる(民法第九五一条)
【補足】建設工事29(建設業法第2条第1項)「現場が分かる建設業法全条文解説 第2条(定義)」…逐条解説~
建設業の29業種は、工事の内容と範囲に基づいて厳格に区分されている。誤った業種で施工すると、建設業法違反に問われるおそれがある。許可取得や実務では、どの工種に該当するかを正確に判断することが重要である。複数の工事が絡む場合は、国土交通省のガイドラインや建設業許可事務ガイドラインを参考にし、必要に応じて専門家に相談することを推奨する。
遺言の有効性と解釈に関する事例問題
最判昭和58年3月18日:遺言解釈において遺言者の真意を探求する際の基準
最判平成13年3月13日:遺言における受遺者の特定と誤記がある場合の解釈
これらの判例は、遺言解釈の基本原則を確立したもので、客観的記載と遺言者の真意との関係、周辺事情の考慮範囲について具体的な指針を示しています。
遺産分割の対象財産についての事例(相続実務家講座)
かつての判例(最判昭和29年4月8日)では、預貯金のような可分債権は、相続開始と同時に法定相続分に応じて各相続人に当然に分割されるため、遺産分割の対象とはならないとされていました。
しかし、この考え方は、共同相続人間の実質的な公平を害する場合があるなどの理由から、最大決平成28年12月19日(民集70巻8号2121頁)によって変更されました。
この最高裁判所大法廷決定により、預貯金は遺産分割の対象となることが明確に示されました。
「地方公共団体におけるリスクマネジメント」R7実施【県庁幹部リスクマネジメント研修講義録】「理論編」冒頭収録
リスクマネジメントは、地方公共団体がより良い行政サービスを提供し、住民の安全・安心を守るための羅針盤です。その羅針盤を正しく使うためには、まず、その土台となる原則(Principles)を以下のように深く理解することが不可欠です。
「現場が分かる建設業法全条文解説 第3条(建設業の許可)」~工事現場から契約書まで、実務で使える逐条解説~
建設業法第3条の逐条解説記事を作成いたしました。この条文は建設業許可制度の根幹となる重要な規定です。許可権者の区分判定:営業所の所在地で決まり、工事を行う場所ではない点 軽微な工事の例外:建築一式工事は特に複雑な判定基準 営業所の実体要件:単なる登記上の住所では不十分 実務では、営業所の増設や移転時に許可区分が変わる可能性があるため、事前の確認が重要です。また、軽微な工事の判定では、建築一式工事の場合、金額要件と面積要件の両方をクリアする必要がある点でよく誤解が生じます。