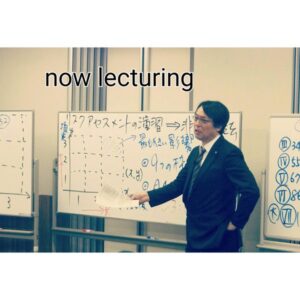【目次】
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 建設業の許可
第一節 通則(第三条―第四条)
第二節 一般建設業の許可(第五条―第十四条)
第三節 特定建設業の許可(第十五条―第十七条)
第四節 承継(第十七条の二・第十七条の三)
第三章 建設工事の請負契約
第一節 通則(第十八条―第二十四条)
第二節 元請負人の義務(第二十四条の二―第二十四条の八)
第三章の二 建設工事の請負契約に関する紛争の処理(第二十五条―第二十五条の二十六)
第四章 施工技術の確保(第二十五条の二十七―第二十七条の二十二)
第四章の二 建設業者の経営に関する事項の審査等(第二十七条の二十三―第二十七条の三十六)
第四章の三 建設業者団体(第二十七条の三十七―第二十七条の四十)
第五章 監督(第二十八条―第三十二条)
第六章 中央建設業審議会等(第三十三条―第三十九条の三)
第七章 雑則(第三十九条の四―第四十四条の三)
第八章 罰則(第四十五条―第五十五条)
附則
…………………………………………………………………………………………………………………
(建設業の許可)
第三条 建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。
一 建設業を営もうとする者であつて、次号に掲げる者以外のもの
二 建設業を営もうとする者であつて、その営業にあたつて、その者が発注者から直接請け負う一件の建設工事につき、その工事の全部又は一部を、下請代金の額(その工事に係る下請契約が二以上あるときは、下請代金の額の総額)が政令で定める金額以上となる下請契約を締結して施工しようとするもの
2 前項の許可は、別表第一の上欄に掲げる建設工事の種類ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる建設業に分けて与えるものとする。
3 第一項の許可は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
4 前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下「許可の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
5 前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
6 第一項第一号に掲げる者に係る同項の許可(第三項の許可の更新を含む。以下「一般建設業の許可」という。)を受けた者が、当該許可に係る建設業について、第一項第二号に掲げる者に係る同項の許可(第三項の許可の更新を含む。以下「特定建設業の許可」という。)を受けたときは、その者に対する当該建設業に係る一般建設業の許可は、その効力を失う。
…………………………………………………………………………………………………………………
建設業法第3条の逐条解説
~建設業の許可の区分~
条文(第3条第1項)
第三条 建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。
一 建設業を営もうとする者であつて、次号に掲げる者以外のもの
二 建設業を営もうとする者であつて、その営業にあたつて、その者が発注者から直接請け負う一件の建設工事につき、その工事の全部又は一部を、下請代金の額(その工事に係る下請契約が二以上あるときは、下請代金の額の総額)が政令で定める金額以上となる下請契約を締結して施工しようとするもの
第3条の趣旨・目的
建設業法第3条は、建設業を営む者に対する許可制度の根幹を定めた規定です。建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するため、原則として建設業を営む者は許可を取得することを義務付けています。
1. 許可権者の区分
(1)国土交通大臣許可(大臣許可)
要件: 二以上の都道府県の区域内に営業所を設ける場合
実例:
- 本社が東京都、支店が大阪府と愛知県にある建設会社
- 本社が福岡県、営業所が熊本県と鹿児島県にある建設会社
注意点: 営業所が1つでも他の都道府県にあれば大臣許可が必要です。例えば、本社が東京都内にあり、営業所が神奈川県に1つだけでも大臣許可となります。
(2)都道府県知事許可(知事許可)
要件: 一の都道府県の区域内にのみ営業所を設ける場合
実例:
- 本社・支店・営業所がすべて東京都内にある建設会社
- 大阪府内にのみ本社と営業所がある建設会社
2. 「営業所」の定義
建設業法上の営業所とは、本店、支店又は常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。
営業所に該当する例:
- 請負契約の見積、入札、契約締結を行う事務所
- 建設業に係る経営業務の管理を行う事務所
営業所に該当しない例:
- 単なる作業所、現場事務所
- 資材置き場、倉庫
- 登記上の本店であっても実体がない場合
3. 許可が不要な「軽微な建設工事」
建設業法施行令第1条の2で定める軽微な建設工事のみを請け負う場合は許可不要です。
一般建設業の軽微な工事
- 建築一式工事: 工事1件の請負代金が1,500万円未満、又は延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
- 建築一式工事以外: 工事1件の請負代金が500万円未満
実例での注意点
ケース1:リフォーム工事
- 住宅リフォーム工事で請負代金480万円の場合
- → 500万円未満なので許可不要
ケース2:建築一式工事
- 木造住宅の新築工事で請負代金1,200万円、延べ面積180㎡の場合
- → 金額は1,500万円未満だが、延べ面積が150㎡以上なので許可必要
4. よくある誤解と注意点
(1)工事場所による誤解
「他県で工事を行うから大臣許可が必要」という誤解がありますが、工事を行う場所ではなく、営業所の所在地で判断します。
正しい例:
- 東京都内にのみ営業所があり、工事は全国で行う → 東京都知事許可
(2)複数業種の許可
同一の許可権者から複数業種の許可を受けることができます。
実例:
- 土木一式工事業と建築一式工事業の両方の許可を都道府県知事から受ける
- とび・土工工事業と鋼構造物工事業の両方の許可を国土交通大臣から受ける
5. 許可の効力
許可は、許可を受けた建設業を営む限り有効ですが、5年ごとに更新が必要です(建設業法第3条の2)。
第3条第2項の解説(建設工事の種類別許可)
条文
建設業法第3条第2項: 「前項の許可は、別表第一の上欄に掲げる建設工事の種類ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる建設業に分けて与えるものとする。」
解説
建設業の許可は、29業種に分類された建設工事の種類ごとに与えられます。
建設工事の29業種(建設業法別表第一)
一式工事(2業種)
- 土木一式工事業
- 建築一式工事業
専門工事(27業種) 大工工事業、左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、電気工事業、管工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、機械器具設置工事業、熱絶縁工事業、電気通信工事業、造園工事業、さく井工事業、建具工事業、水道施設工事業、消防施設工事業、清掃施設工事業、解体工事業
実例
ケース1:複数業種の許可
- A建設会社が「土木一式工事業」と「とび・土工工事業」の両方を営む場合
- → 2つの業種それぞれについて許可申請が必要
ケース2:業種追加
- 既に「建築一式工事業」の許可を持つB社が、新たに「電気工事業」を営む場合
- → 「電気工事業」について業種追加の許可申請が必要
第3条第3項の解説(許可の有効期間)
条文
建設業法第3条第3項: 「第一項の許可は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。」
解説
建設業許可の有効期間は5年間で、更新を受けなければ許可が失効します。
実務上の重要ポイント
更新申請期間
- 許可有効期間満了日の3ヶ月前から30日前まで
- 例:許可有効期間が令和9年3月31日の場合
- 申請可能期間:令和8年12月31日~令和9年3月1日
更新を忘れた場合の実例
- C建設会社が更新手続きを忘れ、令和9年3月31日に許可が失効
- → 建設業を続ける場合は新規許可申請が必要
- → 軽微な工事を除き、工事の請負は違法行為となる
第3条第4項の解説(更新申請中の許可の効力)
条文
建設業法第3条第4項: 「前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下「許可の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。」
解説
適切に更新申請を行った場合、行政の処分が遅れても許可は有効に続きます。
実例
ケース:更新申請中の許可継続
- D建設会社が令和9年1月15日に更新申請を提出
- 許可有効期間満了日:令和9年3月31日
- 行政の審査が長期化し、令和9年4月15日に許可決定
- → 令和9年4月1日~4月14日の間も従前の許可が有効
第3条第5項の解説(更新許可の有効期間の起算)
条文
建設業法第3条第5項: 「前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。」
解説
更新許可の有効期間は、前回許可の満了日の翌日から5年間となります。
実例
更新許可の有効期間計算
- 前回許可の有効期間:平成31年3月31日まで
- 更新申請し、令和元年5月10日に許可決定
- → 新しい許可の有効期間:令和元年4月1日~令和6年3月31日
- (許可決定日の令和元年5月10日からではない点に注意)
第3条第6項の解説(一般と特定の重複禁止)
条文
建設業法第3条第6項: 「第一項第一号に掲げる者に係る同項の許可(第三項の許可の更新を含む。以下「一般建設業の許可」という。)を受けた者が、当該許可に係る建設業について、第一項第二号に掲げる者に係る同項の許可(第三項の許可の更新を含む。以下「特定建設業の許可」という。)を受けたときは、その者に対する当該建設業に係る一般建設業の許可は、その効力を失う。」
解説
同一業種について、一般建設業と特定建設業の許可を同時に持つことはできません。
一般建設業と特定建設業の区別
一般建設業
- 下請代金の総額が4,000万円未満の工事を施工
- (建築一式工事の場合は6,000万円未満)
特定建設業
- 下請代金の総額が4,000万円以上の工事を施工可能
- (建築一式工事の場合は6,000万円以上)
…………………………………………………………………………………………………………………
【国土交通省 令和6年12月6日公表】近年の建設工事費の高騰を踏まえ、特定建設業許可をはじめとする各種の金額要件について見直すこととしました。
2. 政令の概要
(1)特定建設業許可等の金額要件の見直し
(建設業法施行令第2条、第7条の4、第27条、第30条)
| 金額要件 | 現行 | 改正後 |
| 特定建設業許可を要する下請代金額の下限 | 4,500万円 (7,000万円)※1 | 5,000万円 (8,000万円)※1 |
| 施工体制台帳等の作成を要する下請代金額の下限 | 4,500万円 (7,000万円)※2 | 5,000万円 (8,000万円)※2 |
| 専任の監理技術者等を要する請負代金額の下限 | 4,000万円 (8,000万円)※2 | 4,500万円 (9,000万円)※2 |
| 特定専門工事の対象となる下請代金額の上限 | 4,000万円 | 4,500万円 |
※1 建築工事業の場合 ※2 建築一式工事の場合
実例
ケース1:同一業種での移行
- E建設会社が「建築一式工事業」の一般建設業許可を保有
- 事業拡大により特定建設業許可を取得
- → 一般建設業許可は自動的に失効
ケース2:異なる業種での併存
- F建設会社の許可状況
- 土木一式工事業:特定建設業許可
- 建築一式工事業:一般建設業許可
- → 業種が異なるため併存可能
参考資料・根拠条文
- 建設業法第3条(全項)
- 建設業法別表第一(建設工事の種類)
- 建設業法施行令第1条の2(軽微な建設工事)
- 建設業法第27条の23(一般建設業と特定建設業の区分)
- 「建設業許可事務ガイドライン」(国土交通省)
- 「建設業法令遵守ガイドライン」(国土交通省)
実務上の留意事項
1. 業種選択の注意点
- 請け負う工事に応じた適切な業種の許可が必要
- 一式工事の許可があっても専門工事はできない場合がある
2. 更新手続きの管理
- 更新時期の管理システム構築が重要
- 複数業種を持つ場合、業種ごとに有効期間が異なる可能性
3. 許可区分の変更
- 知事許可と大臣許可の変更は新規申請扱い
- 一般建設業から特定建設業への変更時の要件確認
4. 下請代金の管理
- 特定建設業が必要な工事の事前判定
- 下請代金4,000万円(建築一式は6,000万円)の基準管理
建設業法第3条は建設業許可制度の根幹をなす条文で、許可の取得から更新、業種の管理まで建設業経営の基本的枠組みを定めています。特に有効期間の管理と適切な業種選択は、建設業を継続的に営むために不可欠な要素です。