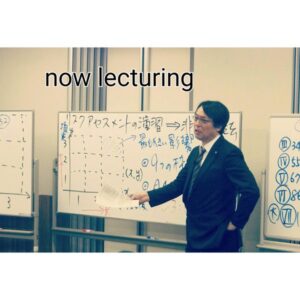◆【事例】被相続人Xは、2023年5月1日に病気のため死亡した。Xの相続人は、配偶者Yと長男Zの2名である。Xは遺言を遺さずに死亡した。死亡時におけるXの財産に関する状況は、以下のとおりであった。
・Xは、自己名義のタワーマンション(評価額8000万円)を所有しており、生前、配偶者Yと共に居住していた。
・Xは、インターネット上の誹謗中傷により名誉を毀損されたとして、加害者Gに対し300万円の慰謝料を請求する訴訟を提起していたが、判決言渡し前に死亡した。
・Xは、所有する乙投資マンション(評価額3000万円)の一室をH社に賃貸しており、H社から月額30万円の賃料収入を得ていた。賃貸借契約では、賃料は毎月末日に翌月分を支払う約束であった。Xの死亡時、H社から2023年4月分の賃料が未払いであった。
・Xは、I銀行に2000万円の普通預金口座を有していた。また、J証券の口座に、時価500万円相当の上場株式を保有していた。
【設問】
(1) 上記の事実を前提として、YとZが遺産分割協議を行う際に、その対象となる財産は何かを、理由とともに説明しなさい。
(2) 相続人間の遺産分割協議がまとまらない状況で、Yが当面の生活費と葬儀費用を支払うため、I銀行に対し、X名義の普通預金口座から450万円の払戻しを単独で求めた。このYの請求は法的に認められるか。また、仮にYが一部でも払戻しを受けられた場合、その後の遺産分割にどのような影響が生じるか説明しなさい。
(どうぞ読者もお考え下さい)
【解説のポイント】
(1) 遺産分割の対象となる財産について
遺産分割の対象となる財産とは、被相続人が死亡時に有していた財産に属する一切の権利義務のうち、その性質上、被相続人の一身に専属するものを除いたものです(民法896条本文)。これを前提に、各財産について検討します。
タワーマンションおよび乙投資マンション(可分か不可分か)
不動産は物理的に分割することが困難な「不可分」の資産です。共同相続されたタワーマンション(評価額8000万円)および乙投資マンション(評価額3000万円)は、遺産分割が完了するまで相続人全員の共有状態(民法898条)となります。
したがって、YとZがどのように分けるかを協議で決める必要があり、両不動産とも遺産分割の対象となります。
(2)加害者Gに対する慰謝料請求権(一身専属性の有無)
慰謝料請求権は、被害者が受けた精神的苦痛を慰藉するためのものであり、被害者個人の感情と密接に結びついているため、原則として一身専属権とされ、相続の対象とはなりません。
しかし、判例(最判昭和42年11月1日民集21巻9号2249頁)は、「被害者が生前に賠償請求の意思を表明していれば、その慰謝料請求権は相続される」との立場をとっています。
本件では、Xは生前に加害者Gに対して訴訟を提起しており、損害賠償を請求する意思を明確に表明しています。
したがって、この慰謝料請求権(300万円)は相続の対象となり、遺産分割の対象にもなります。
(3)H社に対する賃料債権(発生時期による区別)
賃料債権は、発生した時期によって扱いが異なります。
・相続開始時(Xの死亡時)までに既に発生していた賃料債権:
本件の「2023年4月分の未払賃料(30万円)」は、Xの生前に支払期日が到来しているため、被相続人Xの遺産に含まれます。
これは金銭債権であり、かつては可分債権として当然に分割されると考えられていましたが、預貯金債権に関する判例変更の趣旨から、これも遺産分割の対象に含めて協議するのが実務上の一般的な扱いです。
・相続開始後に発生する賃料債権:
Xの死亡日である2023年5月1日以降に発生する賃料(5月分以降)は、相続開始後の財産(賃貸物件たる乙投資マンション)から生じる収益です。
このような金銭債権は、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得すると解されています(最判平成17年9月8日民集59巻7号1931頁)。
したがって、相続開始後の賃料は、原則として遺産分割の対象となりません。
YとZは、それぞれの法定相続分(各1/2)に応じて、毎月15万円ずつの賃料をH社に直接請求できます。
(4)普通預金と上場株式(可分債権の扱いに関する判例変更)
・普通預金(2000万円):かつての判例(最判昭和29年4月8日)では、預貯金のような可分債権は、相続開始と同時に法定相続分に応じて各相続人に当然に分割されるため、遺産分割の対象とはならないとされていました。
しかし、この考え方は、共同相続人間の実質的な公平を害する場合があるなどの理由から、最大決平成28年12月19日(民集70巻8号2121頁)によって変更されました。
この最高裁判所大法廷決定により、預貯金は遺産分割の対象となることが明確に示されました。
したがって、I銀行の普通預金2000万円は遺産分割の対象となります。
・上場株式(時価500万円):株式などの有価証券も金銭的価値を持つ財産であり、当然に遺産分割の対象となります。
【結論】
以上より、YとZの遺産分割協議の対象となる財産は、以下の通りです。
タワーマンション(評価額8000万円)
乙投資マンション(評価額3000万円)
Gに対する慰謝料請求権(300万円)
2023年4月分の未払賃料債権(30万円)
I銀行の普通預金(2000万円)
J証券の上場株式(時価500万円)
(2) 預貯金の仮払い請求とその影響について
【Yの請求は認められるか】
平成28年の判例変更により預貯金が遺産分割の対象となった結果、相続人単独での払戻しが原則としてできなくなり、相続人が当面の生活費や葬儀費用に困るという問題が生じました。
この問題を解決するため、2019年7月1日に施行された改正民法で、預貯金の仮払い制度が創設されました(民法909条の2)。
この制度により、各共同相続人は、遺産分割協議や裁判所の判断を待たずに、単独で一定額までの預貯金の払戻しを金融機関に請求できます。
その上限額は、以下の計算式で算出されます。
払戻し可能額 = (相続開始時の預貯金残高) × (1/3) × (当該相続人の法定相続分)
ただし、一つの金融機関から払い戻せる上限は150万円と定められています。
本件におけるYの払戻可能額を計算すると、
20,000,000円× 1/3 × 1/2 = (Yの法定相続分)3,333,333円
となります。
しかし、同一金融機関からの払戻し上限額は150万円であるため、Yが民法909条の2の制度を利用してI銀行から単独で払い戻せる金額は最大150万円です。
したがって、Yの450万円全額の払戻請求は認められません。
Yは、まずこの制度を使って150万円の払戻しを受け、それでも不足する分については、相続人Zの同意を得て払戻しを受けるか、または家庭裁判所に遺産の分割の審判又は調停の申立てを行い、保全処分(仮分割の仮処分)を求める(家事事件手続法200条2項)といった法的手続きをとる必要があります。
【遺産分割への影響】
民法909条の2の規定に基づき、相続人が預貯金の払戻しを受けた場合、その払戻しを受けた額については、「遺産の一部を分割により取得したものとみなす」と定められています。
これは、払戻しを受けた金額が、その相続人の「遺産の前受け(特別受益に類似した扱い)」と位置づけられることを意味します。
具体的には、YがI銀行から150万円の払戻しを受けた場合、最終的な遺産分割協議において、Yが取得する相続財産の総額を計算する際に、この150万円は既に受け取ったものとして扱われます。
例えば、遺産総額が1億3830万円(マンション8000万+投資マンション3000万+慰謝料300万+未払賃料30万+預金2000万+株式500万)で、
法定相続分通りに分ける場合、Yの取得分は6915万円となります。
しかし、Yは既に150万円を前受けしているため、
残りの遺産から受け取れるのは、
69,150,000円―1,500,000円=67,650,000円相当の財産となります。
このように、共同相続人間の公平が図られることになります。