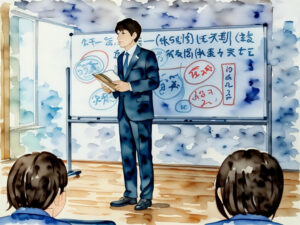企業や組織におけるコンプライアンス違反のニュースは後を絶ちません。多くの場合、違反行為が発覚した際には、その原因として組織ぐるみの隠蔽や個人の倫理観の欠如などが指摘されます。しかし、問題の本質はもっと根深く、人間の心理的なメカニズムに起因していることも少なくありません。
本記事では、コンプライアンス違反が発生する背景にある重要な心理的概念「認知的不協和」に焦点を当て、社会全体の倫理観と組織特有の倫理観の間に生じる「ズレ」が、いかにして違反行為へと繋がっていくのかを解説します。そして、真にコンプライアンスが徹底された組織を構築するために、どのような視点が必要なのかを探求します。
1. 組織の健全性を測るバロメーター「コンプライアンスアンケート」
コンプライアンス体制の構築や改善に取り組む際、まず重要となるのが組織の現状を正確に把握することです。そのための有効な手段の一つが「コンプライアンスアンケート」です。従業員一人ひとりが日々の業務の中で、組織のルールや倫理観についてどのように考え、行動しているのかを匿名性などを確保しつつ調査することで、潜在的なリスクや課題を可視化することができます。
単にルールを知っているか、遵守しているかを確認するだけでなく、より深層心理に踏み込んだ設問を設けることが、実効性のあるアンケートの鍵となります。
2. 心の矛盾が不正を生む?「認知的不協和」の罠
コンプライアンスアンケートにおいて、特に注目すべき項目が「認知的不協和」に関するものです。これは、社会心理学者レオン・フェスティンガーが提唱した理論で、人が自身の中で矛盾する二つ以上の認知(考え、信念、態度など)を抱えたときに感じる不快な心理状態を指します。
例えば、アンケートで次のような問いを設けるとします。
- 問い:仕事でミスをしたときに、あなたは上司にすぐに報告していますか?
「はい」と答えた場合は問題ありません。しかし、「いいえ」と答えた場合、その理由を探ることが重要です。一般的に、ミスをした際には速やかに上司に報告することが、多くの組織で求められる職業倫理であり、就業規則などで定められている場合もあります。
では、なぜ報告しないのでしょうか?
- 「報告してもどうせ怒鳴られるだけだから」
- 「正直に報告すると評価が下がるから」
- 「他の人も小さなミスは報告していないから」
- 「これくらいなら自分でリカバリーできると思ったから」
これらの理由は、「ミスをしたら報告すべきだ」という認知と、「実際には報告していない」という行動との間に生じた矛盾(認知的不協和)を解消するために、自分自身を正当化しようとする心理の表れなのです。
人間は、この認知的不協和という不快な状態を長く維持することができません。そのため、無意識のうちに、どちらかの認知を捻じ曲げたり、新たな理屈付け(正当化)を行ったりして、心の平穏を取り戻そうとします。まさに「盗人にも三分の理」という諺が示す通り、人は自己の行動を正当化せずにはいられない存在なのです。この自己正当化が、時としてコンプライアンス違反への第一歩となる可能性があります。
3. なぜズレる?「社会倫理」と「組織倫理」の避けられない乖離
ここで重要な視点となるのが、「社会全体の倫理観(社会倫理)」と「特定の組織内で通用している倫理観や規範(組織倫理)」の違いです。経験上、この二つの倫理観が乖離することは珍しくありません。
私(代表 中川)自身、学生時代のスポーツチームや、その後の会社勤めを通じて、その組織特有の「暗黙のルール」や「内向きの論理」が、社会一般の常識や倫理観からかけ離れている場面を数多く目の当たりにしてきました。人間は、自分が所属する集団の中で適応し、生き抜くために、その場の規範や価値観に従おうとする傾向があります。いわゆる「ムラ社会の論理」です。
政治の世界でも、所属政党や政権内部の論理が優先され、国民感情や社会全体の倫理観から大きく乖離した判断が行われてしまうことがあります。当事者はその「ズレ」に気づかず、問題が表面化してから初めて事の重大さに気づき、取り返しのつかない事態を招くケースは後を絶ちません。
組織においては、以下のような要因が、社会倫理と組織倫理の乖離を生みやすくします。
- 閉鎖的な組織文化: 外部からの意見を受け入れにくい、同質性の高い組織。
- 過度な同調圧力: 周囲と異なる意見や行動を取りにくい雰囲気。
- 短期的な業績至上主義: 倫理的な問題よりも目先の利益が優先される風潮。
- リーダーシップの欠如: 経営層が倫理的な指針を示せていない、あるいは黙認している。
このような環境下では、従業員は社会倫理よりも組織内の論理を優先するようになり、認知的不協和を感じた際にも、組織に都合の良い自己正当化を行いやすくなります。
4. コンプライアンス違反が発生する核心:認知的不協和と倫理観の歪み
コンプライアンスの本質を考える上で、この「認知的不協和」と「社会倫理・組織倫理の乖離」は極めて重要な要素です。
従業員が認知的不協和の状態から抜け出そうとするとき、「社会倫理に照らして正しい行動をとる」か、「組織倫理(たとえそれが歪んでいたとしても)や自己保身を優先して、不適切な行動をとる」かの選択を迫られます。
組織として、組織倫理を常に社会倫理に近づけようと努力しているか、そのための具体的な仕組みや文化が醸成されているか。これが、コンプライアンス違反の発生頻度を大きく左右するのです。
アリストテレス論理でいうとすれば、コンプライアンスの本質は、自分や組織が周りからどう見られているかを考えることにあるのです。コンプライアンスの研修講師やコンサルティングを20年やっていて自然に私が生み出したどこにもない言葉です。
組織倫理が社会倫理から大きく乖離している場合、従業員は認知的不協和を感じた際に、良心の呵責を感じつつも、不正な会計処理に手を染めたり、データの改ざんを行ったり、不都合な情報を隠蔽したりといった、組織内では「仕方ない」「みんなやっている」と正当化されがちな行動を選択しやすくなります。
5. 違反を防ぎ、持続可能な組織へ:コンプライアンスの本質的な取り組み
では、組織倫理を社会倫理に近づけ、コンプライアンス違反を防ぐためには、具体的にどうすればよいのでしょうか。
これは、私(代表 中川)が日頃から研修や講演でお伝えし、また、ESG投資(環境・社会・ガバナンス)の観点から企業の持続可能性を高めるためのコンサルティングで注力しているテーマでもあります。単にルールを増やしたり、罰則を強化したりするだけでは、根本的な解決にはなりません。
重要なのは、以下のような多角的なアプローチです。
- 心理的安全性の確保: 従業員がミスや問題を正直に報告・相談できる、オープンで風通しの良い職場環境を作る。
- 倫理観の醸成: 経営トップ自らが倫理的な姿勢を明確に示し、全従業員に対して継続的な倫理教育を実施する。社会倫理とは何か、自社の事業活動が社会に与える影響は何かを常に問い続ける姿勢を育む。
- 内部通報制度の活性化: 不正行為を早期に発見し、自浄作用を働かせるための実効性ある内部通報制度を整備・運用する。
- ガバナンス体制の強化: 経営の透明性を高め、取締役会などが経営陣に対する適切な監督機能を果たす体制を構築する。(ESGにおける「G」:ガバナンス)
- 社会との対話: ステークホルダー(顧客、取引先、地域社会、株主など)との対話を通じて、社会からの期待や要請を的確に把握し、経営に反映させる。(ESGにおける「S」:社会)
これらの取り組みを通じて、組織倫理を社会倫理のレベルへと引き上げ、従業員一人ひとりが認知的不協和を感じた際に、安易な自己正当化に逃げるのではなく、倫理的に正しい行動を選択できるような組織文化を醸成することが不可欠です。
6. 多角的な視点が生む本質的な解決策:中川総合法務オフィスの強み
コンプライアンスの問題は、単に法律や規則の知識だけで解決できるものではありません。その背景には、人間の心理、組織の力学、社会全体の価値観、そして時には歴史的・文化的な要因までが複雑に絡み合っています。
中川総合法務オフィスの代表である私、中川は、法律や経営といった社会科学の専門知識に加え、長年の実務経験と人生経験を通じて、哲学や思想といった人文科学、さらには物理学や生物学などの自然科学にも深い関心を寄せ、探求を続けてまいりました。
例えば、認知的不協和という心理メカニズムを、人間の脳機能や進化の過程といった自然科学的な視点から捉え直すこと。あるいは、「正義」や「公正」といった概念を哲学的な視点から深く掘り下げ、組織倫理の根源的なあり方を問い直すこと。また、経済学や経営学の理論だけでは見落とされがちな、非合理的な人間の行動原理を行動経済学などの知見から分析すること。
こうした文理横断的で複眼的なアプローチこそが、複雑化する現代社会のコンプライアンス問題に対して、表層的ではない、本質的な解決策を見出すための鍵となると確信しています。単なる法解釈やルール適用に留まらず、人間と組織、そして社会に対する深い洞察に基づいたコンサルティングを提供すること。それが、中川総合法務オフィスの最大の強みです。
結論:コンプライアンスは「ルール」ではなく「心と文化」の問題
コンプライアンス違反は、単なるルール違反ではなく、組織とそこに属する人々の「心」の問題であり、「文化」の問題です。認知的不協和という普遍的な人間の心理を理解し、組織倫理を常に社会倫理と照らし合わせながら、より健全で持続可能な方向へとアップデートしていく地道な努力が求められます。
中川総合法務オフィスは、法律、経営、心理、倫理、そして近年の生成AIなどの科学的な知見を融合させ、皆様の組織が真に社会から信頼され、持続的に発展していくためのお手伝いをさせていただきます。