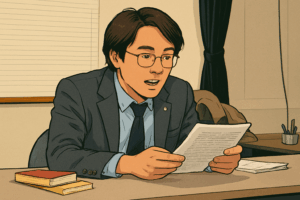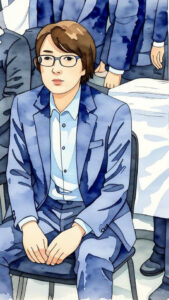「相続」は、誰にでも起こりうる人生の重要な節目です。しかし、準備を怠ると、残された家族間で思わぬトラブルに発展することも少なくありません。京都・大阪を中心に1000件以上の無料相談実績を持つ「相続おもいやり相談室」(中川総合法務オフィス運営)が、改正相続法を踏まえ、特に遺言書を作成しておくべき典型的な、或いは代表的な、或いはないと困るようなケース12を解説します。
当オフィスの代表は、法律や経営といった社会科学分野はもちろん、哲学・思想などの人文科学、さらには自然科学にも深い知見を有しております。単なる法律手続きの解説に留まらず、長年の経験と幅広い視点から、相続問題の本質に迫ります。
遺言書作成を強くおススメする典型的な5つのパターン
【第1位】子どものいない夫婦
(1)夫婦の一方死亡時に配偶者の「親」が生きていた場合
遺留分の定めにより、親は二分の1の三分の1で少なくとも六分の1の強い権利を持つので、配偶者名義の財産を自分の名義にする、預貯金を払い戻そうとするなどの時に、全く無視できないであろう。同意と印鑑証明書がすんなり出てくるかどうか。
遺言を書いておけば、遺留分の権利は改正相続法で債権に変わったので、遺言の効力が優先して、自分名義に圧倒的にしやすくなろう。
殊に、嫁と姑の関係等で義理の親との関係が微妙な時は遺言が不可欠であろう。
(2)夫婦の一方死亡時に配偶者の親は亡くなっていたが「兄弟姉妹」がいた場合
この場合は、兄弟姉妹には遺留分がないので、何もせずに放っておけば、四分の1の権利主張がされてかなり苦労することは目に見えている。
是非とも、遺言で「全財産を配偶者に相続させる云々」の一文を入れよう。
…………………………………………………………………………………………………………………
第一〇四二条(遺留分の帰属及びその割合)
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一
2相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第九百条及び第九百一条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。
…………………………………………………………………………………………………………………
【第2位】相続人がいない人
この場合に、本当に相続人がいないのかきちんと調べていなくて、世間話などから勝手に判断して思い込んでいるだけの時もある。無料法律相談でも、相続が専門でなくていい加減なことがあるから気を付ける必要がある。
大学の講義で、「笑う相続人」の話をローマ法の時代からの蘊蓄を傾けて乾教授等著名な大学教授が何回かいろいろな事例で興味深く話してくれたことがある。繰り返し同じことを言うが、孤独で侘しい学生時代に京都御所の横にあった広小路校舎の講義とそこにあった図書館だけが今でも光っているよ。
配偶者の兄弟姉妹とは次第に疎遠になっていき全く音信不通になっている場合も京都での相続おもいやり相談室の無料相談でしばしばある。実は同じ京都に姪が住んでいて権利を主張してきたのだ。
その背景には、戦後の民法改正の影響もあって、甥や姪にまで、親戚付き合いや一体性などが消滅して、年賀状などのやり取りをしない時代になってしまった。情けないことだ。
いずれにしろ、遺留分の関係でも遺言があった方が圧倒的にいい。
なお、相続おもいやり相談室の当職はこの時は、寄付を勧めている。しかし、元の勤務先や世話になった病院や福祉施設まではいいが、それ以上になるとなかなかモチベーションが上がらないので、決まりにくいのだ。
「日本財団 遺贈寄付サポートセンター」なども悪くはないかもしれないが、当職は何回かのこの団体とのやり取りでちょっと嫌になって辞めている。理由は想像にお任せするが、一言だけ言うと、寄付についてしつこいのは性に合わない。寄付は元は善意でしょう。それを忘れないように。
【第3位】相続時にトラブルになりそうな(起こしそうな)相続人がいる場合
まず、アルツハイマーや病気で事理弁識能力が低い相続人がいる場合は、遺言書がないと、遺産分割協議なるが話し合いに参加できないので、急いで成年後見人等を選任し、相続人の代わりに遺産分割協議に参加してもらうことになる。これはかなり難儀なのと時間がかかる。
遺言書があれば、遺留分の点を除き、遺言内容のままで権利関係がほぼ確定していく。
また、相続おもいやり相談室の当職も経験したことが何度もあるが、外国に居住している相続人、これは普通のことになってしまったし、その外国が領事館などの関係で電話がうまくつながって手続きが進む場合もあれば、そもそも電話そのものに苦労することがある、当職もゆっくりとであれば簡単な会話は可能であるが、早口で英語を話された分には手続き依頼や交渉は無理である。
どこの外国に住んでいるかわからない場合はもうお手上げで裁判所の公示送達などを利用するしかなくなるが、日本に住んでいる場合でも何度も苦労した。
まるで探偵のように、恐らくここに住んでいるはずとひそかに立って見張っていたことも一度や二度ではない。寒かったなー。怪しかっただろうなー。
そもそも、遺産分割協議は相続人全員で行う必要があるので、行方不明者を加えないでした遺産分割協議は無効なのだ。当たり前のことであるが。そこで、家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申立てをし、家庭裁判所の許可を得て、行方不明者の代わりに財産管理人が協議に参加することになる。
ぜひとも、このようなことが予想される場合は完全ではないが、間違いのない人に財産を相続させるように遺言して、もしも将来帰ってきて遺留分の請求があったら渡すことにすればいいのだ。
また、当職も細部までわからない利害や感情などからの色々な理由で被相続人の財産に強い執着がある相続人がいる場合には、何度も遭遇している。残念ながら、相続おもいやり相談室の当職は短答式は数回合格しても最終司法試験に合格しなかった悲しい人なので、交渉をするわけにはいかず、委任状に基づいてやらせてほしいと頼むしかないのでそうしてやっている。
それにしても、この頃よく聞くそういう権利主張だけをして倫理的に大疑問の方の決まり文句は、「貰えるものは貰っておけとみんな言いますので」だ。人ごみをすり抜けて走っている姿が目に浮かぶよ。
そこで、自分がかかわった方の財産管理や遺言では、このような可哀そうな方が出てこないように最大限の努力をしているのだ。
資産があって一流と言われているトンデモ弁護士を雇って、声の大きい方が得することの無いようにしませんか。善人が苦労しないように遺言書を作りましょうや。
【第4位】相続人の数が多い(実務的には対等地位が3人以上)場合は遺言書が有効
3人以上の対等地位の相続人がいると相続における協議での人間関係が難しくなる。被相続人との関係で三人三様だからである。また、相性の問題もある。被相続人との人間関係の濃淡もある。
また、高齢化社会で寿命が延びると、先に子供が死んだり兄弟姉妹が死んだりとするのが当たり前なので現代社会では必然的に相続人は増えているのである。もっとも少子化も同時に進んでいるのでもうあと10年もすれば様相は変わるだろうが。
そこで、親族の関係も疎遠になっていて、その中で自分に近い人に相続させることが普通であって、その時は遺言書が有効なのである。
また、離婚率のピークは平成時代の終わりに過ぎたが、被相続人が離婚してから再婚するときに前婚でもうけた子どもがいると、再婚後の子供と対等の相続権を持つ。すっかり、前婚の配偶者とのみ生活していているから何の主張もしてこないと思ったら現代社会でそういう例はほぼ相続おもいやり相談室の当職の経験ではない。ほぼ揉めるのだ。
相続放棄を迫ってもそうはいかない。ドラマみたいだが、被相続人から前婚の子供がいたことを全く知らずに人生を送ることもあるのだ。このような境遇の人生を送った被相続人は遺言書が有効である。誰に何を与えるか決めておくとよいだろう。
なお、相続人には入ってこないであるが、永い人生でお世話になった人や法人に何らかの遺贈をした場合もあろうが、そういう場合も他の相続人との関係でもめないように遺言書で書いておくとよい、相続おもいやり相談室の当職も遺言書作成のインタビューやカウンセリングで詳しく聞いて原案に盛り込んでいるが、そうしておけば、遺言執行者である当職に小言は言ってきても従う。
なお、寒々とした話だが、被相続人が亡くなったときにタンスなどから自筆証書遺言が発見されたときに、相続人がこの遺贈を実行しない可能性が高い。つい先だって経験した話であるが、法律相談に行った弁護士が見せなくていいといったとのことである、倫理の欠片もないのか。
【第5位】事業承継したいときには遺言は不可欠
将来自分の子どもに事業を継がせたい時には、会社ではなく個人で事業を営む場合に、死亡すれば本人名義の預貯金口座が凍結されるため、速やかに相続手続ができなければ従業員や取引先にお金が払えず、事業に支障をきたす。この時に最も早く凍結が解除されるのは、相続おもいやり相談室の当職ではほぼ5日、遅くとも10日あれば充分である。ただし、自筆証書遺言は検認に時間がかかる(改正相続法による場合も保管がある)が、公正証書遺言の正本をほぼ相続おもいやり相談室の当職は預かっているので早い。
また、株式会社の場合は、後継者に事業承継するためには、株式の大半を相続させる必要があり、遺言書がない場合、事業に関わらない相続人も株式を保有することになり、経営権の集中が困難になる。後継者に事業承継したいのならば、自社株式、事業用不動産・動産(車両、機械備品など)、特許権などの知的財産権、その他経営に関わる権利を、遺言で集中的に相続させるのが有効である。
遺言書作成の必要性がかなり高い代表的な3つのパターン
法改正により相続のルールも変化しています。ご自身の状況に合わせて、遺言書の必要性を考えてみましょう。
【第1位】特定の相続人に全財産を遺したい場合
法定相続人が複数いる状況で、特定の誰か一人に全財産を相続させたいと強く願うケースです。例えば、長年にわたり献身的に介護してくれた子、事業の後継者として期待する子などが考えられます。
ポイント:
- 遺留分への配慮: 他の法定相続人には、法律で最低限保障された相続分である「遺留分」があります。全財産を一人に相続させる遺言は、他の相続人から「遺留分侵害額請求」を受ける可能性が高いことを理解しておく必要があります。
- 遺留分侵害額請求とは?: 改正相続法により、遺留分を侵害された相続人は、侵害額に相当する金銭の支払いを請求できるようになりました。以前のように不動産そのものを取り戻す(物件的効果)ことはできませんが、金銭的な請求は可能です。遺言の効力自体が無くなるわけではありません。
- 事前の対策:
- 遺留分対策: 生命保険金の受取人を指定するなど、遺留分請求に備えた資金対策を検討します。
- 証拠の確保: 生前贈与があった場合は、その証拠(通帳のコピーなど)を保管しておくと、後の話し合いで役立つことがあります。
- 遺留分の放棄: 相続開始前に、家庭裁判所で遺留分放棄の手続きをとってもらうことも考えられますが、相手の協力が必要であり、実務上は稀です。
相続おもいやり相談室では、遺留分や特別受益(生前贈与など)について十分にご説明し、ご本人の強い意志を確認した上で、このような遺言書作成をお手伝いしたケースも少なくありません。「専門家に背中を押してほしい」というお気持ちで来られる方もいらっしゃいます。大切なのは、ご自身の意思を明確にし、起こりうる事態に備えることです。
【第2位】特定の財産を特定の相続人に遺したい場合
「自宅不動産は配偶者に、収益物件である賃貸ビルは長男に、株式や預貯金は次男に」というように、どの財産を誰に相続させるかを具体的に指定したい場合、遺言書は非常に有効です。これも京都の資産家の方では多く経験しました。
ポイント:
- 公平性への配慮: 各財産の評価額は異なるため、相続人間で不公平感が生じないよう配慮が必要です。例えば、不動産を相続する相続人と、金融資産を相続する相続人の間で、取得する財産価値に大きな差が出る場合があります。
- 調整措置: 生命保険金の受取人を指定したり、預貯金の分配割合を調整したりすることで、相続人間の公平性を図る工夫が考えられます。
遺言書で明確に指定することで、相続人間の無用な争いを避け、円満な財産承継を実現しやすくなります。
【第3位】分割しにくい不動産が主な財産である場合
相続財産が預貯金などの金融資産だけであれば、法定相続分に応じて比較的容易に分割できます。しかし、財産の大部分が不動産(特に自宅など)で、相続人が複数いる場合、その分割方法は簡単ではありません。
不動産の分割方法:
- 現物分割: 不動産そのものを相続人の一人(または複数人)が取得する。
- 代償分割: 特定の相続人が不動産を取得する代わりに、他の相続人に対して代償金(現金など)を支払う。
- 換価分割: 不動産を売却し、その売却代金を相続人間で分配する。
- 共有分割: 相続人全員が、それぞれの相続分に応じた持分で不動産を共有する。
ポイント:
- 遺産分割協議の難航: 遺言書がない場合、相続人全員による遺産分割協議が必要になりますが、不動産の分け方を巡っては意見が対立しやすく、協議が難航・長期化するケースが後を絶ちません。当職の経験上も、どの分割方法をとっても、全員が完全に納得することは難しく、後味の悪さが残ることが多いです。
- 共有分割のリスク:
- 権利関係の複雑化: 共有状態は、将来的な売却や大規模修繕(特に賃貸物件の場合、銀行融資など)の際に、共有者全員の同意が必要となり、意思決定が困難になるリスクがあります。
- 経済的な不都合: 賃貸物件の場合、立地や収益性、将来価値が物件ごとに異なるため、どの物件を誰が(または共有で)取得するかで揉める原因となります。
- 次世代への問題先送り: 共有状態のまま相続が繰り返されると、権利関係がさらに細分化・複雑化し、管理・処分がより一層困難になります(いわゆる「塩漬け不動産」化)。しかし、実務では結構多い。
- 配偶者居住権の新設: 改正相続法では、遺産分割などで配偶者が住み慣れた自宅に住み続けられなくなる事態を防ぐため、「配偶者居住権」という権利が創設されました。これにより、配偶者は自宅の所有権を取得しなくても、一定期間または終身、無償で住み続けることが可能になります(ただし、遺言や遺産分割協議での設定が必要です)。遺言では普通にみられるようになっています。
- 専門家選びの重要性: 税理士によっては、相続税対策のみを重視するあまり、土地と建物の所有者を別にする、安易に共有にする、といった分割方法を提案することがあります。これは後々、権利関係を複雑にし、深刻なトラブルの原因となりかねません。法律面・実務面を熟知した専門家への相談が不可欠です。
- 特殊なケース(使用貸借・借地権など):
- 使用貸借: 相続財産である建物に、親族などが無償で住んでいる(使用貸借)場合、遺言でその居住権を保障しておかないと、建物を相続した他の相続人から立ち退きを求められる可能性があります。特に、行政が関わるような再開発計画などが持ち上がると、問題が複雑化することもあります。当職も、長岡京市の駅前道路拡張で犠牲になった方の相談を何回も受けました。権利主張できないのは分かるから行政は非常に高飛車でした。アカンよ。
- 借地権: 借地に建てた建物を相続する場合、遺言で土地の借地権と建物の所有権を同一人物に相続させるように指定しないと、地主との間で転貸借の問題が生じ、最悪の場合、借地契約を解除されるリスクもあります。
不動産は価値が大きいだけに、その分け方は相続において最も揉めやすいポイントの一つです。遺言書で明確な指針を示しておくことが、円満相続への鍵となります。
その他、遺言書作成を検討すべきケース
上位3つのパターン以外にも、以下のような場合には遺言書の作成を強くおすすめします。
1.「囲繞地(いにょうち)」にある不動産を相続させる場合
所有する土地が、他人の土地に囲まれていて公道に直接接していない(いわゆる「袋地」)場合があります。普段は隣地の所有者の好意で通行させてもらっていても、その所有者が変わったり、関係が悪化したりすると、通行を拒否されるリスクがあります。
対策:
- 通行地役権の設定・登記: 隣地所有者の承諾を得て、通行する権利(通行地役権)を設定し、法務局で登記しておくことが最も確実な対策です。これにより、土地の所有者が変わっても通行権が保障されます。
- 遺言書への記載: 通行地役権を設定した旨や、設定に向けた協議状況などを遺言書に記載しておくことで、相続人に状況を正確に伝え、将来の紛争予防に繋がります。
- 囲繞地通行権(民法第210条): 法律上、袋地の所有者は公道へ出るために最低限必要な範囲で周囲の土地を通行する権利(囲繞地通行権)が認められていますが、通行の場所や方法は制限され、場合によっては償金の支払いが必要になることもあります。やはり、地役権設定が望ましいでしょう。
不動産調査では、図面だけでなく現地を確認することの重要性が、このようなケースからもわかります。
2.高価な動産(貴金属、美術品、知的財産権など)がある場合
金の延べ棒、高級腕時計、ブランド品、美術品(絵画、壺など)、あるいは書籍、音楽、発明などの著作権や特許権といった知的財産権も、価値ある財産です。金融資産や不動産と異なり、物理的な分割が難しいものが多く、評価も容易ではありません。
ポイント:
- 処分の難しさ: 「相続人間で適当に分けてほしい」と遺言に書いても、価値観の違いや思い入れなどから、すんなりとは決まらないことが多いのが実情です。遺言執行者を指定していても、動産の分配は苦労が伴います。
- 具体的な指定: 可能な限り、「この絵画は長女に」「この著作権は事業を継ぐ次男に」のように具体的に指定するか、「その他一切の動産は〇〇(個人名)に相続させる」といった包括的な指定をしておくことが望ましいです。
- 形見分けとの区別: 法律上の相続財産とは別に、故人を偲ぶ品物を近親者で分け合う「形見分け」の慣習があることにも留意が必要です。遺言書で指定する財産と、形見分けとして譲りたいものを区別しておくと良いでしょう。
近年、知的財産権の価値はますます高まっています。これらの権利を誰に承継させるかは、遺言で明確にしておくべき重要な事項です。
3.祭祀(さいし)の承継や先祖代々の財産がある場合
お墓や仏壇、系譜などを維持管理し、法要などを主宰する「祭祀主宰者」を遺言で指定することができます(民法第897条)。
ポイント:
- 祭祀承継者の指定: 特定の子どもや親族に、先祖供養を引き継いでほしい場合に指定します。
- 祭祀費用の負担: 葬儀、納骨、法要などには相当の費用がかかります(当職の経験では100万円程度は必要になることも珍しくありません)。祭祀を主宰する負担を考慮し、その費用に充てるための財産(預貯金など)を別途、祭祀主宰者に相続させる旨を遺言書に明記しておくことを強くおすすめします。後から費用負担をめぐって他の相続人と揉めるケースは少なくありません。
- 葬儀・埋葬方法の希望: 散骨(樹木葬、海洋葬など)や永代供養、墓石への刻印、墓所の改葬(お墓の引っ越し)などの希望は、遺言書の「付言事項」として記載できます。ただし、遺言書は死後すぐに開封されるとは限らないため、葬儀や納骨に関する希望は、生前にエンディングノートに記したり、葬儀を任せたい人に直接伝えたりしておくことがより確実です。
- 先祖代々の土地: 長年受け継いできた土地などを、特定の家系(例えば長男の家系)に引き継がせたいという希望がある場合も、遺言書が有効です。相続によって土地が細分化されるのを防ぐことができます。
- 世代を超えた承継(信託の活用): 特定の土地や事業用資産を、子だけでなく、孫、ひ孫の代まで特定の血筋に承継させたいという場合は、遺言書だけでは実現できません。このような場合は、「後継ぎ遺贈型受益者連続信託」という信託契約を生前に結ぶか、遺言による信託(遺言信託)を設定する方法があります。手続きは複雑になりますが、より長期的な財産承継の設計が可能です。
事業用資産の承継においても、事業継続のために資産が分散しないよう、遺言書や信託を活用することが重要になります。
4.マイナスの財産(借金・ローンなど)の承継を指定したい場合
借金やローンなどの債務(マイナスの財産)は、原則として法定相続人が法定相続分に応じて相続することになります。これは、お金を貸している債権者を保護するためです。
ポイント:
- 遺言による負担者の指定: 遺言書で、「住宅ローン付きの自宅を相続する長男が、そのローン全額も引き継ぐ」というように、特定の相続人に債務を集中して負担させる指定をすることは可能です。
- 債権者の同意: ただし、この指定が法的に有効であっても、債権者(銀行など)との関係では、債務を引き継ぐ人の返済能力(資力)が問題となります。債権者が同意しなければ、他の相続人も引き続き返済義務を負う可能性があります。遺言で指定する場合は、事前に債権者(金融機関など)に相談しておくことが望ましいでしょう。
まとめ:円満な相続のために、今できること
遺言書は、ご自身の最後の意思を明確に示し、残された家族への思いやりを形にするための重要なツールです。特に、今回ご紹介したようなケースに当てはまる方は、お元気なうちに遺言書の作成を検討されることを強くおすすめします。
相続は、法律、税金、不動産、そして何よりも家族関係が複雑に絡み合う問題です。中川総合法務オフィスの代表は、法律家としての専門知識に加え、経営、哲学、歴史、さらには科学的な知見まで含めた多角的な視点から、皆様の状況を深く理解し、最適な解決策を一緒に考えます。
「相続おもいやり相談室」では、京都・大阪を中心に、初回無料相談を実施しております。遺言書の作成はもちろん、相続に関するあらゆるお悩みについて、どうぞお気軽にご相談ください。あなたの、そしてご家族の未来のために、私たちが全力でサポートいたします。
無料相談のご案内
中川総合法務オフィスでは、相続・空き家問題に関する豊富な実績と深い専門知識を基に、お客様一人ひとりの状況に応じた最適な解決策をご提案いたします。
京都・大阪エリアで1000件超の相続無料相談を実施し、多くの複雑な案件を解決に導いてきた経験を活かし、法律・税務・実務の各面から総合的にサポートいたします。
初回の30分~50分は無料で相続の相談をお受けしております。ご自宅、病院、介護施設、または当事務所での面談、さらにはオンラインでの相談も可能です。
お気軽にお問い合わせください。
予約電話番号:075-955-0307 メールフォーム:https://compliance21.com/contact/