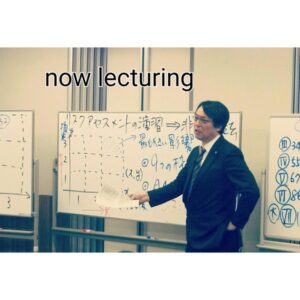1.労働法に関する使用者のコンプライアンス環境整備責任
近年、企業における労働コンプライアンスの重要性は増すばかりです。労働法規の遵守は、企業の持続的な成長と信頼確保に不可欠であり、そのための環境整備は使用者の責務と言えます。
(1) 個別労働関係における親会社のコンプライアンス責任
サービス残業やハラスメントといった労働問題が発生した場合、その責任は直接的な雇用主である会社だけでなく、親会社にも及ぶ可能性があります。これは、親会社がグループ全体の内部統制を監督する責任を負っていると考えられるためです。
会社法では、取締役会が業務執行の決定や取締役の職務執行の監督を行う権限を持つことが定められています(会社法第362条)。さらに、取締役会は、法令や定款に適合した業務執行体制を整備する義務を負っています(会社法第362条第4項第6号、会社法施行規則第100条)。
この規定に基づき、親会社は子会社における労働環境についても適切な監督を行い、コンプライアンス違反が発生しないよう体制を整備する責任を負うと解釈できます。例えば、子会社でサービス残業やハラスメントが常態化している場合、親会社の内部統制が十分でなかったとして、コンプライアンス上の責任を問われる可能性があるでしょう。
(2) 集団的労働関係のコンプライアンス
一方、労働組合法においては、労働者のコンプライアンス環境整備の責任は、原則として当該会社が負うものとされています。労働組合は、労働者の権利を守るための団体であり、使用者との団体交渉などを通じて労働条件の改善を目指します。
しかし、親会社が子会社の労働組合活動に不当な介入を行うなど、労働組合法に違反する行為があった場合には、親会社も責任を問われることがあります。
2.労働法のコンプライアンス時代における意識改革:無視から尊重へ
かつての日本では、企業活動においては利益追求が優先され、労働法規は二の次、あるいは無視される傾向が見られました。会社は社会にとって善であり、その発展のためには多少の法規違反はやむを得ない、といった考え方も一部には存在したかもしれません。
しかし、現代においては、「働き方改革」に代表されるように、労働者の権利や労働環境に対する社会の目は厳しくなっています。労働者は単なる労働力ではなく、企業を支える重要なステークホルダーとして、人的資本として、新たに認識されるようになり、その尊重は企業の信頼と評価に直結します。
1985年のトレッドウェイ委員会発足や、1992年のCOSOレポート「内部統制:統合的枠組み」の発表以降、日本においても規範遵守は企業のレピュテーションリスクに関わる重要な経営課題として認識されるようになりました。労働現場の状況は、組織内部の問題から社会全体の問題へと広がりを見せており、労働者の信頼を失った組織は、コンプライアンスの観点から見ても立ち行かなくなると言えるでしょう。
3.労働法規範の変遷:判例法理から実定法による規制法理へ
労働法規範は、従来の判例法理中心の運用から、より明確な実定法による規制へと移行する傾向にあります。
例えば、解雇の有効性については、以前は民法の権利濫用法理が適用され、具体的な判断は裁判所の解釈に委ねられる部分が大きく、予測可能性に課題がありました。
しかし、平成20年施行の労働契約法第16条では、解雇が無効となる要件が明文化されました。
(解雇) 第十六条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
この規定は、最高裁判所の判例(高知放送事件:昭和52年1月31日)の考え方を踏襲したものであり、解雇の有効性判断における客観性と合理性がより重視されるようになりました。
さらに、労働施策総合推進法では、パワーハラスメントといった優越的な関係を背景とした言動問題についても、その定義や事業主の措置義務が明確に定められるようになりました。これは、労働現場におけるハラスメント防止を強化し、労働者が安心して働ける環境を整備するための重要な進展と言えます。
特に、中小企業においては、これまで労働法規への対応が遅れているケースも見られましたが、改正労働施策総合推進法の全面施行(2022年4月1日)により、大企業と同様のハラスメント対策が義務付けられることになり、コンプライアンス経営の重要性が一層高まっています。
これらの動きは、労働法規範が、個別の裁判例の積み重ねによる解釈(判例法理)から、法律によって明確に定められたルール(実定法による規制法理)へと変化していることを示しています。
4.コンプライアンス違反によるリスク:民事・刑事・行政上の責任
労働コンプライアンスに違反した場合、企業は様々なリスクに直面します。
- 民事上の賠償責任: 労働者がコンプライアンス違反によって損害を被った場合、企業は民法上の安全配慮義務違反に基づき、損害賠償責任を負う可能性があります。
- 会社法上の責任: 取締役は、法令を遵守し、会社のために忠実に職務を行う義務を負っています(会社法第355条)。労働関連法規の違反は、取締役の善管注意義務違反や忠実義務違反にあたる可能性があり、第三者に対して損害賠償責任を負うこともあります(会社法第429条)。
- 刑事上の責任: 労働基準法などの労働関連法規には、違反行為に対する罰則が定められており、悪質な場合には刑事罰が科されることがあります。
- 行政法的なサンクション: 厚生労働省は、労働基準法などに違反した企業、特に悪質なケースについては、企業名を公表するなどの行政指導や制裁措置を行うことがあります。これは、いわゆる「ブラック企業」対策の一環として行われています。
- レピュテーションリスク: コンプライアンス違反は、企業の社会的評価を大きく損なう可能性があります。SNS等での批判の拡散は、企業イメージの低下や採用活動への悪影響、取引先からの信頼失墜につながる可能性があります。
このように、労働コンプライアンス違反は、企業にとって多方面にわたるリスクを引き起こす可能性があり、その対策は経営における最重要課題の一つと言えるでしょう。
まとめ:労働コンプライアンス研修の重要性
今日の労働コンプライアンスは、かつての「無視」される存在から、企業経営において最も重要な「尊重」すべき要素へと180度変化しました。このような最新の動向を踏まえ、企業全体で労働コンプライアンスに対する意識を高め、適切な対応策を講じることが不可欠です。
中川総合法務オフィスでは、これまでの豊富な労働法コンプライアンス研修の実績に基づき、全国の企業様に向けて、階層別・組織メンバー全員を対象とした最新の労働コンプライアンス研修やコンサルティングを提供しております。労働コンプライアンスに関するお悩みや研修ニーズがございましたら、お気軽にご相談ください。