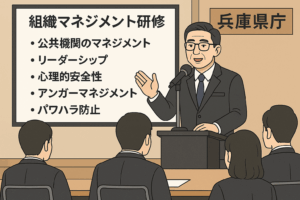インターネット、特にSNSの普及は、私たちの生活やビジネスに多くの利便性をもたらしました。一方で、匿名性を悪用した誹謗中傷やプライバシー侵害といった問題も深刻化しており、個人だけでなく企業のレピュテーションにも甚大な被害をもたらすケースが増えています。このようなネット上の不当な投稿に対し、法的にどのように対応できるのでしょうか。
本記事では、ネット上の誹謗中傷問題に対処するための重要な法律である「プロバイダ責任制限法」について、2022年の法改正による変更点も踏まえながら、その仕組みや具体的な手続き、開示請求できる情報について詳しく解説します。
1. 深刻化するネット上の誹謗中傷問題とその難しさ
ネット上の誹謗中傷は、瞬く間に拡散し、一度書かれた情報は完全に削除することが難しい場合もあります。特に、匿名での投稿は発信者を特定することが困難であり、被害は深刻化しやすい傾向にあります。
かつて、インターネット上の情報発信元を個人が独自に特定することは極めて困難でした。投稿に使われたIPアドレスから契約しているISP(インターネット・サービス・プロバイダ)や大まかな所在地が推測できることがあっても、その先にいる個人を特定するには、ISP側が任意に情報開示に応じるケースは少なく、警察の捜査や裁判所の命令といった強制力のある手続きが必要となるのが実情でした。
このような背景から、インターネット上の権利侵害に対して、被害者がよりスムーズに、かつ法的に発信者の情報開示や投稿の削除を求めることができるように整備されたのが、「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」、通称「プロバイダ責任制限法」です。この法律は、平成14年(2002年)5月27日に施行され、その後の社会状況の変化に合わせて数度の改正を経て、現在に至ります。
2. プロバイダ責任制限法による誹謗中傷への対応
プロバイダ責任制限法は、インターネット上で他人の権利を侵害する情報が流通した場合において、プロバイダ(特定電気通信役務提供者)の損害賠償責任を制限するとともに、権利侵害を受けた者が、プロバイダに対して権利侵害情報の削除請求や発信者情報の開示請求を行う権利を定めた法律です。
この法律があることで、被害者は法律に基づきプロバイダに削除や情報開示を求めることが可能となり、これにより誹謗中傷を行った者に対して、民事での損害賠償請求や、内容によっては刑事告訴を行う道が開かれます。
(1) プロバイダ責任制限法の仕組み
この法律は、インターネット上の情報の自由な流通と、個人の権利保護のバランスを図るものです。プロバイダは、原則として他人の情報流通による損害について直ちに責任を負うわけではありませんが、権利侵害を知っていた場合や、送信防止措置(削除など)を講じることが技術的に可能な場合は責任を負うことがあります(第3条)。
一方で、プロバイダが権利侵害情報の送信防止措置を講じた場合でも、発信者に対する賠償責任を免れるための要件も定められています(第3条第2項)。これは、プロバイダが権利侵害情報への対応を過度に恐れて、表現の自由を不当に制約することのないように配慮されているためです。
そして、被害者にとって最も重要なのが、発信者情報の開示請求に関する規定です(第4条)。
(2) 2022年法改正:情報開示請求手続きの大きな変更
プロバイダ責任制限法による発信者情報開示請求は、長らく課題を抱えていました。従来の開示手続きでは、一般的に以下の二段階の手続きが必要でした。
- コンテンツプロバイダへの開示請求: 投稿が掲載されたウェブサイトやSNSの運営者(コンテンツプロバイダ)に対し、投稿時のIPアドレスやタイムスタンプの開示を求める。
- 経由プロバイダ(ISP)への開示請求: 1で得たIPアドレスをもとに、そのIPアドレスを割り当てていた経由プロバイダ(いわゆるISP)に対し、契約者情報(氏名、住所など)の開示を求める。
この二段階の手続きは、時間と費用がかかるだけでなく、各段階で裁判が必要になることも多く、被害者の負担が大きいという問題がありました。
この問題を解消するため、令和4年(2022年)10月1日に改正プロバイダ責任制限法が施行され、「情報開示命令事件に関する裁判手続」が創設されました。
これにより、被害者は一つの裁判手続きの中で、コンテンツプロバイダに対するIPアドレス等の開示請求と、経由プロバイダに対する契約者情報の開示請求を一括して行うことが可能になりました。これは、被害者の負担を大幅に軽減し、迅速な権利回復につながる画期的な改正です。
(3) 開示請求できる発信者情報
プロバイダ責任制限法に基づき開示請求できる発信者情報は、総務省令で具体的に定められています(プロバイダ責任制限法第四条第一項の発信者情報を定める省令)。主な情報は以下の通りです。
- 氏名または名称
- 住所
- 電子メールアドレス
- 侵害情報に係るIPアドレス
- 侵害情報に係る携帯電話端末等からのインターネット接続サービス利用者識別符号(携帯キャリアなどが割り当てる識別番号)
- 侵害情報に係るSIMカード識別番号
- 上記のIPアドレスや識別番号が使用された年月日及び時刻
- 携帯電話番号(※2022年改正により追加され、開示される可能性のある情報が拡充されました)
これらの情報が開示されることで、誹謗中傷を行った発信者を特定し、損害賠償請求などの次のステップに進むことが可能になります。
3. 削除請求・情報開示請求の具体的な手続き
ネット上の誹謗中傷に対する削除請求や発信者情報開示請求は、以下のような流れで進むのが一般的です。
- 証拠保全: 誹謗中傷の投稿があるURL、スクリーンショット、投稿日時など、証拠となる情報を正確に記録します。魚拓などのウェブアーカイブも有効な場合があります。
- 権利侵害性の判断: 投稿内容が法的に保護される権利(名誉権、プライバシー権など)を侵害しているか、専門的な観点から判断します。単なる批判や感想は権利侵害とならない場合もあります。
- 削除請求: サイト管理者やコンテンツプロバイダに対し、投稿の削除を求めます。任意の削除に応じない場合や、緊急性が高い場合は、裁判所へ削除の仮処分を申し立てることもあります。
- 発信者情報開示請求(裁判手続):
- コンテンツプロバイダへの開示命令申立て: 投稿が掲載されたサイトの運営者等に対し、投稿時のIPアドレスやタイムスタンプの開示を求める裁判手続きを行います。
- 経由プロバイダへの開示命令申立て: 1で得たIPアドレス等をもとに、そのIPアドレスを使用していた経由プロバイダ(ISP等)に対し、契約者の氏名、住所、電話番号などの情報開示を求める裁判手続きを行います(2022年改正により、上記コンテンツプロバイダへの開示命令と合わせて行うことが可能になりました)。
これらの手続きは、専門的な知識と経験が必要となります。特に2022年の法改正による新しい裁判手続きは、適切な対応を行うためには法律の専門家である弁護士に依頼することが不可欠です。
関連情報や手続きに関するガイドラインは、総務省やテレコムサービス協会などのウェブサイトでも提供されています。 (参考:総務省 国民向け情報「インターネット上の誹謗中傷等に関する相談窓口」https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/ihoyugai.html ※リンク先は変更される可能性があります)
4. 法を超えた視点:ネット上のリスクとコンプライアンス
インターネット上の誹謗中傷問題への対応は、単に法的な手続きを知っているだけでは不十分です。この問題の根底には、情報の非対称性、集団心理、倫理観の欠如、あるいは技術そのものの特性など、様々な要因が複雑に絡み合っています。
中川総合法務オフィスの代表である中川恒信は、長年にわたり企業のコンプライアンス体制構築や不祥事対応に関わる中で、法律や経営といった社会科学の視点に加え、人間の本質や社会のあり方を深く探求することの重要性を痛感してきました。哲学や思想といった人文科学、そして情報技術の基盤をなす自然科学への深い知見は、ネット社会で起こる問題を多角的に捉え、本質的な解決策を見出すための糧となっています。
ネット上のリスクは、法的な側面だけでなく、組織文化、従業員の意識、情報管理体制といったコンプライアンスの根幹に関わる問題でもあります。表面的な対処療法にとどまらず、なぜそのような問題が起きるのか、どうすれば根本的に防げるのかを、幅広い視野から考察し、実践的な対策に落とし込んでいくことが、現代の企業には求められています。
5. まとめ
ネット上の誹謗中傷は、個人や組織にとって看過できない重大なリスクです。プロバイダ責任制限法は、被害者が法的に対処するための強力なツールを提供しており、特に2022年の法改正により、その手続きはより迅速かつ効率的に行えるようになりました。
しかし、法的手続きには専門知識が不可欠であり、また、ネット上のリスク管理は法的な対処だけでなく、組織全体のコンプライアンス体制の強化という視点から取り組む必要があります。
中川恒信によるコンプライアンス研修・コンサルティングのご案内
インターネット上のリスクを含む、現代社会における企業のコンプライアンス課題に対し、実践的かつ本質的な解決策をお求めでしょうか?
中川総合法務オフィスの代表である中川恒信は、これまでに850回を超えるコンプライアンス等の研修を担当し、多くの企業・団体でコンプライアンス意識の向上と体制強化に貢献してまいりました。
また、不祥事を起こした組織のコンプライアンス態勢再構築にも深く関与し、危機管理と再発防止に向けた実効性のあるアドバイスを提供してまいりました。現在も、複数の企業の内部通報の外部窓口を担当しており、生きたリスク情報を組織の改善に繋げる活動を行っています。
その豊富な経験と幅広い知見から、マスコミからも不祥事企業の再発防止策についてしばしば意見を求められるなど、その専門性は高く評価されています。
法律論に留まらない、人間の心理や組織のダイナミクスを深く理解した中川恒信の研修・コンサルティングは、参加者や組織に深い気づきと具体的な行動変容を促します。インターネット上のリスク対応はもちろんのこと、ハラスメント防止、情報セキュリティ、組織不正の防止など、貴社の様々なコンプライアンス課題に対し、実践的なアドバイスを提供いたします。
是非とも、中川総合法務オフィスの代表 中川恒信に、貴社のコンプライアンス研修やコンサルティングをご依頼ください。
- コンプライアンス研修: 1回あたり30万円(税別)から承っております。貴社の状況やご要望に合わせて内容をカスタマイズいたします。
- コンサルティング: 貴社のコンプライアンス体制構築、内部通報制度の整備、ネットリスク対応など、具体的な課題解決に向けたコンサルティングは、内容に合わせて別途お見積もりいたします。
お問い合わせは、お電話または当サイトの相談フォームより承っております。
お電話:075-955-0307
相談フォーム:https://compliance21.com/contact/ (※サイトのURLに合わせて調整ください)
貴社がコンプライアンスを経営の重要な柱として、持続的に発展していくためのお手伝いができれば幸いです。お気軽にご相談ください。